キャンパス内に設置された電波望遠鏡から誰も見たことのない宇宙を見る!
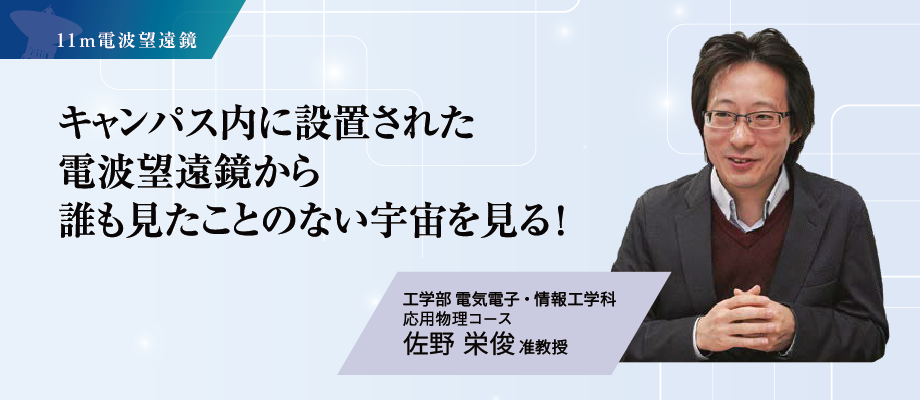
電波望遠鏡は、可視光で見る光学望遠鏡と違い、電波を収束させて天体を観測します。
岐阜大学工学部の宇宙科学研究室では、11m電波望遠鏡を使って宇宙研究に挑み、特色ある開発研究に取り組んでいます。
星の誕生と終焉の謎に迫る
ビッグバン直後の宇宙には水素とヘリウムの2元素のみが存在し、大量の水素ガスが集積されることで星を形成しました。その内部でつくられた物質が、星の最期の大爆発などを通して宇宙空間へ放出され、現在の多様な元素に満ちた宇宙となりました。質量の大きな星は爆発後にブラックホールを形成する場合があります。
宇宙科学研究室では11m電波望遠鏡を用い、こうした「星の誕生と終焉の現場」を研究しています。
2014年には、他大学や国立天文台の電波望遠鏡とのVLBI観測※で、天の川銀河の中心にあるブラックホールの高感度定点観測に成功。現在は、太陽と同程度の質量を持つ星が一生の終わりに発する「メーザー」と呼ばれる強力な電波を捉えることで、元素放出の仕組みの全容解明に挑んでいます。
太陽の8倍以上の質量を持つ巨大星が超新星爆発時に発するX線やγ線と、電波で調べられる水素ガスの分布を組み合わせた多波長解析により、単一の波長領域では見えない「誰も見たことのない宇宙を見る」研究は、世界をリードしています。南米チリにある名古屋大学のミリ波望遠鏡NANTEN2と連携し、星のもとになる水素ガスの世界初の宇宙地図を描くことで、星の誕生の仕組みにも迫ります。
※ VLBI: Very Long Baseline Interferometry(超長基線電波干渉法)の略。離れた場所にある複数の電波望遠鏡を使い、まるで巨大な一つの電波望遠鏡のように高い「視力」で宇宙を観測する方法。
宇宙の研究は多面的な力を育む
電波望遠鏡を持つ7大学のうち、岐阜大学は唯一、学内に電波望遠鏡が設置されています。学生は宇宙の研究を通じて、工学に加え数学や物理といった理学的な理解を深め、あらゆる分野に応用可能なロジカル思考などのスキルを身に付けます。学生が世界最先端の研究テーマを発案することも。
チリの大型電波望遠鏡「アルマ」を使用するための観測提案 [採択率約15%] では、昨年度は、宇宙科学研究室から16件を応募し、学生の提案課題2件を含む10テーマが採択されました。人生を懸ける価値ある研究と、成長著しい人材の育成を楽しみながら、岐阜から宇宙を切り拓いていきます。


地殻変動の観測用として通信総合研究所が東京で運用した後、同じ用途で2002年に岐阜大学に移設。岐阜大学宇宙電波観測所を設立し、現在は、電波天文学の研究用として活用。
| 観測帯域 | 21.5-23.8GHz(波長約1.35cmの「センチメートル波」を受信) |
|---|---|
| 駆動速度 | 3.0度/秒(パラボラ面が2分で1周の速度で駆動し、人工衛星の追尾も可能) |












