学生主体の生物多様性保全・自然再生プロジェクト:鷭ヶ池自然再生プロジェクト
岐阜大学の敷地内にある鷭ヶ池。かつては、水生植物が生育し、多数の野鳥が飛来していましたが、半世紀近く放置されていたため、湿地的環境の劣化と生物多様性の低下が進行しています。環境への問題意識を高く持ち、自然再生に取り組む学生に話を伺いました。


岐阜大学キャンパス移転時の自然保護活動が契機となって、昭和50年に「自然保存地」に指定された約2万㎡の池。トウカイヨシノボリをはじめとする貴重な動植物が生息し、岐阜市最大のカモ類の飛来地として知られている。

 岐阜大学環境サークル G-amet
岐阜大学環境サークル G-amet
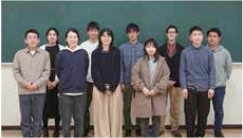
平成30年に有志によって設立されたサークル。学生が主体となって環境の課題について取り組み、多くの人の環境に対する意識を向上させることを目標としている。 活動理念は「わたしたちだからできること。」、令和6年2月現在は18名が所属。
活動理念は「わたしたちだからできること。」、令和6年2月現在は18名が所属。
「鷭ヶ池自然再生プロジェクト」は、岐阜大学の敷地内にある鷭ヶ池に水鳥「バン」が戻ってくるような環境づくりを目的としたプロジェクトです。サークル活動の一環として、4、5年ほどかけて現地を調査し、自然環境の劣化と生物多様性の低下の仕組みを研究してきました。現在は、調査結果をもとに効果的な再生方策を検討し、人工的な復元作業を段階的に実施しているところです。

植物について調査を行ってきた。サークルとして
は、文系・理系の枠を超えた分野横断的な検討を
目指している。
そもそもプロジェクトが始まったのは、サークルの創立メンバーが講義を受けた際に池の存在を知り、調べていく中で問題意識が芽生えたのがきっかけ。歴史をさかのぼると、もともと鷭ヶ池周辺は湿地帯で、バンの集団繁殖地だったようです。その後、1970年代に入り、集中豪雨や岐阜大学の移転工事に伴って生態環境が大きく変化。加えて、外来生物の侵入や水質の悪化も重なって、バンの姿は消えてしまいました。以後、半世紀近く放置され、学生や教員の認知度も低下する一方でした。
当サークルは「わたしたちだからできること。」を活動理念としており、鷭ヶ池の自然再生は学生だからこそできることだと考えています。社会人や企業などが主体になるとマネタイズなどを考える必要があると思いますが、私たちは比較的自由な時間がありますし、動植物や環境問題について考えることはシンプルに楽しいです。サークルには互いに刺激し合えるメンバーが集まっていて、毎週の定例会を楽しみにしています。
 また、本プロジェクトでは、鷭ヶ池を含む岐阜大学柳戸キャンパスを1つの実験場に見立て、学生や地域の方が多様な生物に触れるとともに、環境保全のための知見を身につけた人材を育成する場になることを目指しています。私たちも調査研究の手法や科学的知見に基づいた保全方策を学ぶことにもつながっていて、楽しみながら知識と経験を蓄積できています。"百聞は一見に如かず"といわれるように、環境学習も実際に見て触れることが大切だと思いますので、生物多様性の保全に取り組むとともに、調査研究の場を守っていきたいです。
また、本プロジェクトでは、鷭ヶ池を含む岐阜大学柳戸キャンパスを1つの実験場に見立て、学生や地域の方が多様な生物に触れるとともに、環境保全のための知見を身につけた人材を育成する場になることを目指しています。私たちも調査研究の手法や科学的知見に基づいた保全方策を学ぶことにもつながっていて、楽しみながら知識と経験を蓄積できています。"百聞は一見に如かず"といわれるように、環境学習も実際に見て触れることが大切だと思いますので、生物多様性の保全に取り組むとともに、調査研究の場を守っていきたいです。

鷭ヶ池に小規模な実験区を設置。抽水植物の生育
場所の再生が、人工的にエコトーンを造成するこ
とによって可能か検証している。
加えて、私たちが大事だと考えているのが、プロジェクトを学内外の協力者と協働して進めていくこと。やはり、自分たちだけでは視野が狭く、専門知識も不足していますので、専門家の協力が不可欠。そして、さまざまな立場の方と関わっていく中で、鷭ヶ池に関心を持つ人のコミュニティを広げていきたいからです。そのために活動内容をオープンにして、SNSやWEBサイトで発信をしています。少しずつではありますが、学内や他大学のサークルからも認知されるようになってきましたので、引き続き活動を積極的に発信していきたいです。
昨年度からはエコトーンの造成を始めました。エコトーンとは、陸域と水域の境界になる水際環境のこと。水の深さや土の水分条件がゆるやかに変わっていく場所があることで生物の多様性が生まれます。かつて存在した多くのエコトーンは失われましたが、人工的に移行帯をつくることで、新たな湖沼・湿地生態系を創出できるはずです。水底に根を張り、バンなど水鳥の住み家となる抽水植物が増えてこれば、彼らにとって心地よい場所になると思いますので、地道にこのプロジェクトを続けていきたいと思っています。












