先輩の声 volume 03

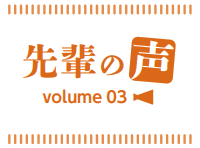
時には喧嘩もできる仲間を作ることが大事。
意見をぶつけるからこそ拓ける世界がある。
岐阜県農政部長
1988年 農学部農学科卒業
足立 葉子 さん
岐阜市出身。岐阜大学農学部農学科を卒業。農学職として岐阜県庁に入庁し、さまざまな所属で農業振興施策に携わる。農業経営課長、農政部次長を歴任し、令和5年4月からは農政部長(現職)に就任。食料生産をはじめ、販路拡大、担い手育成、農村の維持、家畜防疫、スマート農業、農福連携など、幅広い分野を担う農政部の指揮を執る。
農業とは無縁の幼少時代。高校の先生の勧めで農学部へ

活気のある楽しい日々を過ごした。
私は岐阜県岐阜市出身で、父はエンジニア、母は薬剤師という家庭で育ち、農業とは関わりのない環境で幼少期を過ごしました。実家のすぐ近くにキャンパスがあり、岐阜大学は常に身近な存在でしたね。高校に入学した当初は、教育学部への進学を検討していたのですが、岐阜大学農学部出身の化学の先生から、当時注目を集めていたバイオテクノロジーの話や、農家を支援する農業改良普及員という仕事があることを聞き、実学である農学部に面白さを感じて進路を変更しました。農学部に進学したと聞いたご近所さんからは「農家じゃないのに、どうして農学部に行くの?」なんて不思議がられたものです。

練習に遠征にと忙しい毎日。入庁後も、県の代表
として全日本実業団バドミントン選手権にも出場。
入学後は、中学・高校と続けてきたバドミントン部に所属し、練習と遠征に明け暮れていました。中学時代の先輩と大学で再会するという嬉しい出来事もあり、3年次までは東海リーグの1部昇格を目指し、まさにバドミントン漬けの毎日でしたね。親からは「農学部に入ったのか、バドミントン部に入ったのか分からない」と言われていました。
3年後期からは、白菜とキャベツ(カンラン)を掛け合わせたバイオ野菜「ハクラン」の研究に取り組み、組織培養の最新技術の一端に触れながら、実験や調査を経て結果を出す面白さを味わいました。私が所属する園芸学の研究室はとても人気で、30名ほどの農学科の学生のうち、毎年5~7人ほどが所属する大所帯。大学院2年生の先輩を筆頭にみんなで行動することが多く、研究も食事会も活気があり、とても楽しい毎日でした。
果樹の普及員として現場へ。「ありがとう」の言葉が励みに
岐阜県庁に入庁したのは昭和63年のこと。農学職として果樹の普及指導活動を担当することになり、揖斐農業改良普及所に赴任しました。当時は女性の農業改良普及員が少なく、200名ほどの中でわずか4名。地元の農家や関係者の方と交流するため、お酒の席に参加する機会などもあり、大変でした。ただ、柿の大きさを測定して生育状況を調べるなど、自分なりに課題を見つけて計画を立て、農家の方に「ありがとう」と感謝される成果が残せた時にはやりがいを感じました。その後、県庁に異動するまで7年間ほど普及員を務めましたが、農業の現場の空気を肌で感じられたこと、何か物事を進める時にはキーパーソンを見つけることの大切さを学べたことは、その後の業務にもさまざまな場面で生かされています。
担い手育成プロジェクトなど、前例のない挑戦に次々取り組む

クラブの皆さんと食育イベントを開催。
県庁では岐阜フラワーショーの初回開催を担当しました。生産から販売まで、関係者と合意形成しながら新しいものを創り上げる業務を経験し、大きな達成感を得られました。また、10年ほど前、岐阜県の新規就農者を育成する「担い手育成プロジェクト」の立ち上げに参画したことも印象深い出来事の一つです。農家を目指す方の人生を大きく左右する事業だけに、みんなで知恵を出し合い、県が開発したポットでトマトを作る技術を活用することで、経験がなくても1年ほど研修すれば就農できる仕組みを構築。これまでを振り返ると、前例のないことへのチャレンジの連続だったと思います。
農政部長となった現在は、農業・農村の振興のため、畜産、水産、農業土木、流通販売、さらには海外輸出などにも取り組んでいます。肥料や飼料、光熱費の高騰で厳しい状況が続く中、農業に携わる皆さんが明るい気持ちで仕事に向き合える持続可能な農業を実現すること、またそれを支える県職員が自分の仕事に自信を持ち、前向きに輝ける職場を作り上げていくことを目指しています。
時には喧嘩ができる友人を作り、真剣に意見をぶつけ合う経験を
学生時代の経験で役に立ったのは、友人や先輩、後輩、恩師などとの人脈でしょうか。研究室では、柿の「ヘタ博士」として知られる中村三夫先生、その後に赴任された福井博一先生にお世話になりましたが、福井先生には卒業後もさまざまな形で相談に乗っていただきました。また、研究室のメンバーと共にいろんな活動に取り組む中で、みんなでワイワイと意見を出し、新たなものを創り上げるプロセスを学べたことも大きな財産だと感じています。今の学生の皆さんにはこうした経験をたくさん積んでもらえたらと願っています。
単に友人を作るだけでなく、喧嘩もできる仲間を持つことが大事です。時には意見をぶつけ合い、互いの隙間を埋めていく。こうした経験を積むことが、社会に出てから必ず生きてきます。学生時代の失敗はいくらでも挽回できます。ぜひ臆することなく、いろんなことに挑戦してほしいですね。












