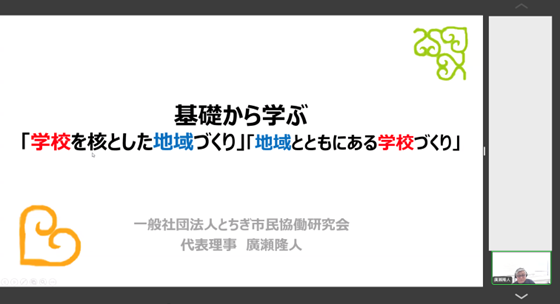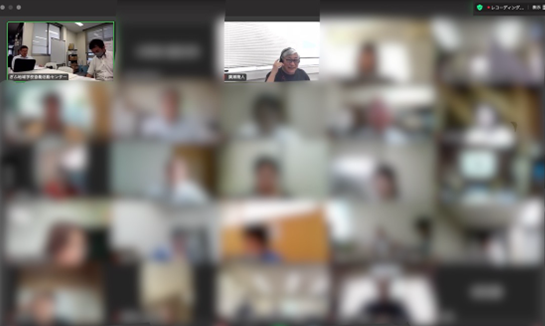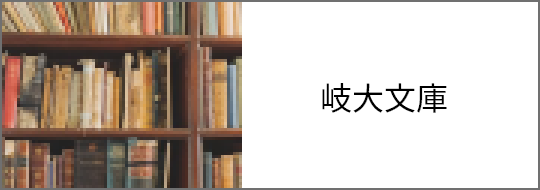令和7年度 第1回地域学校協働活動推進員等育成研修を実施しました
6月24日(火)に、ぎふ地域学校協働活動センターの人材育成事業の一つである「第1回地域学校協働活動推進員等育成研修」をオンラインで実施しました。
ぎふ地域学校協働活動センターは、岐阜県と岐阜大学が共同で設置した組織で、地域・自治体・学校における「地域学校協働活動」を支援・促進し、子どもたちの成長を地域全体で支えるとともに、活動を通じて地域の活性化を図ることを目的としています。
同センターでは、「人材育成・確保」、「調査研究」、「普及促進」の3つの分野で活動しており、今回の研修は、「人材育成・確保」に関する取組の一環として、市町村や社会教育関係団体と連携し、地域学校協働活動推進員などを育成する目的で行います。今年は、地域学校協働活動推進員に加え、岐阜県子育て支援研修の修了者も研修対象とし、地域学校協働活動の基礎知識や実践方法について全4回の研修を行います。今年は96名の受講申込がありました。
第1回である今回は、益川浩一センター長からセンターの概要や研修の目的に関する説明に始まり、廣瀬隆人氏(一般社団法人とちぎ市民協働研究会代表理事/元宇都宮大学教授・元北海道教育大学教職大学院教授)より「基礎から学ぶ『学校を核とした地域づくり』・『地域とともにある学校づくり』」と題した講演を行いました。講演では、「学校を核とした地域づくり」、「地域学校協働活動」、「地域づくり」といった概念を解きほぐしながら、地域のコーディネーターとなる推進員の役割について事例を交えた説明がありました。
その後、グループに分かれ、各地における実践の状況や課題について意見交換を行いました。それぞれの地域における事例や、各参加者の立場からの思いなどを話し合いました。
最後の質疑応答では、講師ー参加者だけではなく、参加者間でも盛んに言葉が交わされました。「やはり、学校を中心としてしまうと、学校教員の負担が多くなるのではないか」という質問に対して、廣瀬氏は「教員に動いてもらおうとする前提があるから、負担をかけてしまう。推進員である自分が動いて地域と学校を繋いでいくことによって活動は進んでいく。学校に何かをやらせると考えるのではなく、学校に入り込んで様子を見た上で、地域の人とどんなことをできるかを考えていくのが大切」と助言がありました。また、「外国籍の家族とつながるためのヒントがほしい」、「学校長の先生にどのように働きかけると良いか」、「推進員や活動している人の間での連絡手段は何か」といった具体的な疑問について情報を共有する機会となりました。
廣瀬氏は、「それぞれの地域で、自分のできる形でやれば良い。無理をしては負担感が出て続かない。その地域でできること・その地域でしかできないことをやれば良い。それぞれの地域で今皆さんがやっておられることで良い」と述べ、今後推進員等として地域で活躍されていく参加者を後押しされました。
次回の育成研修は8月26日(火)に実施する予定です。受講者が今回の育成研修で学んだことを生かし、それぞれの地域でより一層活躍されることを期待しています。