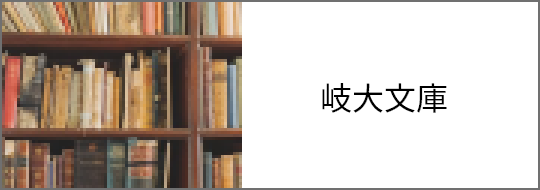岐阜大学医学教育開発研究センター(MEDC) 第88回医学教育セミナーとワークショップを開催
岐阜大学医学教育開発研究センター(MEDC)は、5月22日(水)~24日(金)の3日間にわたり、第88回医学教育セミナーとワークショップを開催しました。また、第25回国公私立大学医学部・歯学部教務事務職員研修とあわせて開催し、延べ185名が参加しました。
今回は4つのワークショップとウェビナーを実施しました。ワークショップの中の一つ「学生の社会情動的スキルを育むアプローチを考える」は、4年ぶりに岐阜大学にて対面開催し、非認知能力とその教育に関する話題について、全国医療機関のさまざまな医療職で卒前卒後教育に関わる方々と議論する機会となりました。はじめに、非認知能力の基本的な捉え方に関して講義があり、非認知能力の定義、よく利用されるフレームワーク、発達段階との関係性について共有し意見交換を行いました。また、ワールドカフェ方式で、非認知能力に大きく影響を受けていそうな困った学習者や教育者事例を扱うテーブルを設け、活発な議論が行われました。その後、今後の医療者教育の中で実践できそうな工夫について共有し、発表を行いました。参加者からは「ワールドカフェならではの多彩な工夫やコツを共有することができ有意義だった」と好評を博しました。
また、ワークショップ「学習ポートフォリオ評価:基本と現状」では、国公私立大学医学部・歯学部教務事務職員研修の共同企画として実施しました。岡山大学病院の猪田宏美先生と東京医科大学の油川ひとみ先生がポートフォリオの実践例について紹介しました。教員と事務職員が共通のテーマでディスカッションする貴重な機会となりました。
さらに、Webinar企画として「非認知能力から見た医療系教育への示唆」を実施しました。早稲田大学の小塩真司先生を講師に迎え、近年注目を集めている「非認知能力」をテーマとし、感情制御や好奇心、動機づけなど広く非認知能力に関連する心の働きについて理解を深め、教育活動の中で何らかの形で活かしていくためのヒントについて議論しました。特に医学部は認知能力を重要視してきた背景を踏まえ、非認知能力が医療者教育に導入されることは、大きなインパクトを与える可能性があることを示唆しました。今後一層の非認知能力を育む教育実践が開発・研究されることが期待されます。
MEDCでは、医学教育共同利用拠点として我が国の医療者教育の普及・開発・向上に寄与すべく、年3回「医学教育セミナーとワークショップ」を開催しています。次回の第89回は10月26日(土)に愛知医科大学と共同で開催し、8月下旬からMEDCホームページにて参加者を募集予定です。


早稲田大学小塩真司教授(上)、
MEDCセンター長 西城卓也教授(中)、
MEDC 川上ちひろ准教授(下)