先輩からのメッセージ
教育学部

学校教育教員養成課程
心理学コース 3年
望月 せいかさん
一人ひとりに寄り添うことのできる存在に。
将来は地元である岐阜県で働きたいと考えていたこと、教員免許と心理系の資格が両方取得できる大学への進学を希望していたことなどがあり、学校教育講座心理学コースに入学しました。現在は、心理学の観点から児童生徒の発達や学習の過程について学んでいます。特に印象に残っている講義は「障害者障害児心理学」。この講義では、発達障がいのある子どもや大人への接し方などを学び、障がいに対する意識を変えることができました。障がいについての予備知識があれば、先入観で決めつけることがなくなり、相手の気持ちに寄り添って考え、行動できるのではないかと感じています。ここでの学びは教育現場に限らず、日常生活でこそ生きてくるはずです。将来は教員になるのか、心理学の仕事に就くのか定まっていませんでしたが、2 年生次に教育実習へ参加したことで、より一層子どもと関われる仕事に就きたいという想いが強くなりました。これからも夢に向かって頑張っていきたいです。

学校教育教員養成課程
美術教育講座 4年(投稿時)
塚本 春菜さん
「美術って面白い」と思えるような教育に携わりたい。
高校時代は美術部に所属。「将来は美術に携わる仕事をしたい」と考える中で、美術教員を選択肢に加えられるよう教育学部に進学しました。岐阜大学にはすばらしい先生方が多く、中でも工芸の先生は実際に目の前で作品を作って見せてくださるので、分かりやすく技術を学ぶことができます。卒業制作では木工作品を制作。粘土や金属では表現できない温かさや親しみやすさ、人間がこれまで木を使ってさまざまな生活道具を作ってきた歴史も学びながら作品を仕上げました。また、学び以外でも大学生活を充実させたいと思い、落語研究会に入会。新春寄席など、地域の方々からの依頼を受けて舞台に上がっています。毎回緊張しますが、笑ってもらえた時は喜びと達成感でいっぱいです。教育実習でも、生徒たちの前でハキハキと話すことができ、経験が生かされていると実感しました。今後は一人でも多くの生徒に「美術って面白い!」と思ってもらえる教師になれるよう、努力していきたいと思います。

学校教育教員養成課程
英語教育講座 4年
星野 佑輔さん
生徒一人ひとりと真摯に向き合う教員を目指す。
親身になって生徒に対応してくれた中学時代の恩師に憧れて教育学部に入学しました。授業では、やはり教育実習が特に印象に残っています。もともと自分から積極的に話しかけるタイプではなかったのですが、教員は恩師のように一人ひとりの生徒と向き合うことが大切だと実感。生徒に自分から話しかけることを心がけたことで苦手意識を払拭でき、人として成長できたと思います。 また、実習では模擬授業で学んだことや、ゼミの研究テーマである効果的な英語授業の仕方を実践。実際に単語が覚えられない生徒に対して勉強法を教えたりしながら、自分も伝える力も身につけることができました。岐阜大学は、1年次からの教職トライアルや教職リサーチなどで早い段階から教育現場で経験を積み、実習に挑めるのが魅力だと思います。これまでの経験を生かして、将来は生徒それぞれに合わせたコミュニケーションをとって、生徒たちが楽しく、安心して過ごせるようなサポートができればと考えています。

大学院教育学研究科 総合教科教育専攻
令和元年度修了 小学校教員
中瀬 亮さん
教師としての働き方や指導の要点を深く学べました。
岐阜大学への進学を決めた一番の理由は、「ACT プラン・プラス」に魅力を感じたからです。ACT プラン・プラスとは、1 年時の岐阜大学教育学部附属小・中学校での観察実習に始まり、4 年間にわたり教育現場でさまざまな経験を積めるプログラムのこと。数多くの実習を通じて、現職の先生たちが授業以外にどんな仕事に取り組んでいるのか、具体的な働き方を詳しく知ることができるのが魅力です。実習では「発問の重要性」に気付かされました。先生は何気なく言葉を発したつもりでも、語尾やニュアンスの細かな違いが気になり、子どもたちが発問の意図とは違うことを考えてしまうことがあります。「どんな発問をすれば、教えたいことを考えてもらえるのか」を常に工夫する大切さを実感しました。現在は大学院へと進学し、教鞭を執るための知識を深める一方、糖尿病を予防する機能性食品の研究開発にも取り組んでいます。教師とは直接関わりのない分野ですが、さまざまな経験を積むことで、勉強以外にもたくさんのことを伝えられる先生になりたいです。
地域科学部

地域政策学科 4年
山田 琴葉さん
文系・理系に関係なく幅広い分野を勉強でき、
多角的な視点を養えるのが地域科学部の醍醐味。

地域政策学科 4年
山田 琴葉さん
私の地元である一宮市は「七夕まつり」で有名ですが、普段は駅前の中心市街地でも閑散としています。そこで地元を盛り上げるための方法を学んでみたいと思い、地域科学部を選びました。将来の夢や目標が明確に定まっていない中、高校の先生が「幅広い分野を学べるのが魅力」と勧めてくれたのも大きかったです。私がゼミで専門的に学んでいるのは「環境心理学」。以前から人の感情の変化に興味があったのがきっかけです。身の回りの空間や色彩が人間の心理に与える影響について考える学問で、ペンの色の違いが記憶にどのように影響するのかなどを研究しています。そのほか、消費者の目線で販売する大切さを学ぶ「マーケティング論」も面白かったですし、授業の一環で美濃加茂市役所のインターンシップに参加し、移住者向け情報を発信する Web 記事の制作に携われたのもいい経験になりました。社会人になってからも地域科学部で学んだ多角的な視点を生かして頑張っていきたいです。

地域文化学科 4年
髙須 啓太さん
悩みを抱えている人を支援する仕事に就きたい。
さまざまな地域をフィールドに研究できるということと実家から距離が近かったことが、岐阜大学に進学を決めた理由です。始めは地域経済学を学びたいと考えていましたが「教育・心理学」などの授業を受けるうちに、教育福祉に興味を持ちました。2 年生後期から始まるセミナーでは、青年期の自立などを研究する南出吉祥先生の研究室に所属しています。現在は大学生の孤立や発達障害に関心があり、コミュニケーションのあり方について理解を深めています。また、2年次に受けた、全学共通教育科目の講義「まちづくりリーダー実践」で、援助を必要としていることを周囲に知らせる「ヘルプマーク」の普及活動を行いました。市役所や商店街、ショッピングモールなどを回りながらさまざまな立場の人の話を聞いて、弱者への配慮や情報発信の大切さを学ぶことができました。将来は、社会の中で生きづらさを抱えている人を支援する仕事ができたらと考えています。

地域政策学科
令和3年度卒業
中部電力パワーグリッド株式会社
田口 裕幸さん
ゼミでの時間がかけがえのない思い出。
地域科学部の魅力は幅広い学問に触れることができることだけではありません。私が一番の魅力だと感じたのは、充実したゼミ活動です。地域科学部には、文理を問わず幅広い学問、個性的で魅力的な先生方がそろっており、経済学や法学など、特定の学問に囚われることなく自分の好きなことをテーマに研究できます。私の場合は自分の趣味であるスノーボードを卒論の研究題材としていました。また、他学部よりも早く2年生からゼミに入るので、ゼミで過ごす時間が非常に長くなります。ゼミでは学問を究めることはもちろんのこと、大切な仲間、思い出がたくさんできます。私は宇山ゼミに所属していましたが、必死に研究に打ち込んだ経験、仲間と研究室でパーティを楽しんだこと、学年関係なく真剣に意見をぶつけ合った議論、どれも大切でかけがえのない思い出です。社会人となり、岐阜を離れた今でも、ゼミの仲間とは交流があります。ゼミ選びの際は、たくさん見学に行って、雰囲気や研究内容など自分にぴったりなゼミを見つけてみてください。

地域文化学科 国際教養コース
令和元年度卒業
Affinity Co., Ltd.
保坂 泉さん
地域科学部で研究の楽しさを知れたこと。
海外留学に憧れを持ちつつも、興味のある学問が見つかっていなかった私は、幅広くさまざまな分野から学べる点や、留学の機会が充実している点に魅力を感じ、国際教養コースに進学しました。在学中、オーストラリアの大学で 1 年間の交換留学を経験し、人種や文化背景の異なる学生たちとともに学び、心を通わせられたことに感動しました。帰国後、地域科学部の授業で言語学や第二言語習得論に出会い、人間はどのようなメカニズムで言語を習得するのだろうか?どんな学習法や言語教育が最も効果的なのか?という疑問に科学的に答えていくこの学問に魅了されました。卒業後、この分野の研究が最先端であるイギリスの大学院へ進学し、英語習得や学習教材の研究に取り組みました。現在はイギリスで海外留学を志す日本人学生をサポートしながら、博士課程への進学を目指しています。英語の必要性が高まる今、第二言語習得の研究者として、より効果的で個々の学習者に最適な学習法・指導法を明らかにすることで社会に貢献していきたいと思っています。
医学部医学科
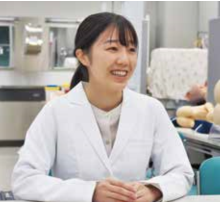
医学科 5年
合田 瀬奈さん
対患者、対医療チームに伝える力を磨きたい。
祖母の病や、私自身岐阜大学病院に入院した経験から自然と医師になりたいと志すようになり、高校生の頃から産婦人科医を目指しています。2 年次の医学研究について学ぶテュトーリアル選択配属では解剖学を選択しました。一から自分で考えながら行う人体解剖実習は困難もありましたが、臓器の構造に対する理解を深めることができました。現在は院内の各診療科を回って実習し現場経験を重ねています。5 年次に産婦人科を回る際は、先生方の患者さんとの接し方、どんな赤ちゃんがいるかなどをしっかりと見て学びたいと思います。座学に傾倒しすぎると現場で柔軟に対応できないこともあるため、実際の患者さんの心に寄り添うことも意識しながら学びを深めていきたいです。学外では、塾講師のアルバイトをしています。どのように言い換えたら生徒に分かりやすく伝わるかなどコミュニケーションについて学べることも多く、この経験を今後に生かしていけたらと思っています。

医学科 6年
山中 真名さん
疾患だけではなく人そのものを診る医師に。
子どもの頃、家族の病気がきっかけで医師という存在に憧れを抱き、高校で本格的にめざすようになりました。岐阜大学を選んだのは、地元の医療に少しでも貢献したいと考えたからです。2年次から救急災害の研究室に所属し、救急現場で必要とされる医学の基礎的な研究を行っています。4年次に行った救急災害訓練では学生が医師役、患者役などに分かれ、実際の大災害を想定して訓練を展開。チームの仲間と声を掛け合いながら実践することを通じて、どんな緊急時も1人で対応しようとせず、仲間で協力して行うことの重要性を学びました。訓練を通して身につけた協働力は、将来、チーム医療の現場で活かすことができると感じています。また学びと並行してバトミントン部や室内合奏団の活動も積極的に行っています。多様な人との出会いで培ったコミュニケーション力で、将来は疾患だけではなく人そのものを診れる医師になりたいです。
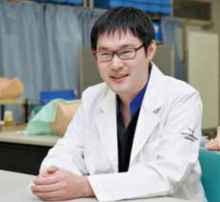
医学科 令和 3 年度卒業
岐阜大学医学部附属病院 研修医
北山 雄一さん
研修医になった今、しっかりと生きています。
高校までは岡山で過ごし、親戚が岐阜にいたこともあって、岐阜大学に進学しました。医者を志したのは、父が食道がんになって看病していた時に、人を助けられる仕事をしたいと思ったからです。学生時代を振り返ると、最初の 4 年間で医師になるために必要な基礎的な知識を身につけ、5年生から臨床実習を行いました。臨床実習では、実際に患者さんと接することで知識を深めたり技術を身につけたりするとともに、医師になる上での責任感が芽生えたと感じています。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、リモート講義など入学前には全く想定してなかったこともありましたが、周りの仲間や先生方のサポートもあり、制限の中でも充実した時間が過ごせました。現在は 研修医として2年間の初期研修の真っただ中。内科や救急、小児科などの診療科を回り、臨床現場での経験を積んでいます。現時点では外科か整形外科を目指していますが、研修を進める中で道を決めていきたいと思っています。
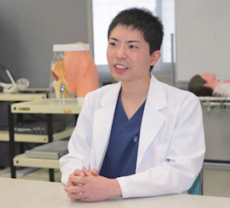
医学科 令和元年度卒業
中部国際医療センター 医師
紀藤 雅典さん
チームで困難を乗り越えたことが今につながっています。
小さい頃、母親が岐阜大学医学部附属病院に入院していて面会で通っていた時に、自分も人を助ける仕事がしたいと思い、地元の岐阜大学に進学しました。学部生の頃は、検体から疾患の原因を検証する「形態機能病理学」の研究に取り組んでいました。ただ、自分だけの学びには限界があるため、仲間と自主的な勉強会を開いて知識を深めていました。また、数人の有志とボート部を立ち上げたことも良い思い出です。最初は、活動するための資金も無かったため、企業を回って寄付金を募ったり、他学部からも仲間を集めたりして、大学にも部活として公認されて大会に出場できるようになりました。ゼロから始めることは大変でしたが、チームで意思疎通を取り、連携する重要性を実感できました。医療現場で働き始めて感じるのは、人と人とのコミュニケーションの大切さです。今後は、大学時代の経験を生かして、チームワークを大切にしながら患者さんの気持ちに寄り添っていけるような内科医を目指していきたいです。
医学部看護学科

看護学科 3年
長屋 真夢さん
グローバルに活躍できる助産師になりたいです。
中学生の頃、踏切の傍で苦しんでいた外国人の妊婦さんを偶然見かけ、そんな人を助けられるようになりたいと思い助産師を目指しました。また、高校でアメリカへの交換留学に行った際に、ホストシスターが助産師だったこともあり、現場での話を聞いてより興味を持ちました。岐阜大学の看護学科に入学して感じたのは、先生のケアが手厚いことです。患者さんのケアをまとめた動画を作ってくださったり、提出物にもコメントを丁寧に書いて戻してくださったりするので、期待に応えたいという気持ちに自然となります。初期体験実習でも、岐阜大学医学部附属病院の看護師さんに同行して、現場での仕事ぶりを早い段階で見ることができ、かなり刺激をうけました。自宅から 1.5 時間~ 2 時間程度かけて通学しているのですが、岐大に来てよかったと感じています。将来は海外でも働いてみたいという気持ちもあるので、語学とスキルとともに、患者さんに寄り添える人間性を磨いていきたいです。

看護学科 2年
苅谷 美有さん
早い段階から実践的な学びが得られるのが魅力。
私が看護師に興味を持ったのは、この世に命が生まれてくることに感銘を受け、将来は出産に関わる仕事がしたいと助産師に憧れたのがきっかけです。中学時代には産婦人科の職場体験を通じて、全てが望まれるお産ではなかったり、育児の悩みで病気になる人がいたりする現実を知り、お母さんたちに寄り添い一人ひとりに合わせた支援ができる助産師になりたいと考えました。岐阜大学を選んだのは、先輩から「地域との関わりが強く、大学病院で1年生から実習できる」とお聞きし、看護師として活躍するうえで早い段階から実践的な学びを得られる点に魅力を感じたからです。今年度から始まった「地域生活体験実習」を通じて、地域の人たちと直接関わる機会が持てたり、グループワークで皆と話し合いながら物事を決めていく経験が積めたりと、看護師として働くうえで役立つ学びがとても多いと感じています。先生方の手厚い支援が受けられる「助言教員制度」があるのもありがたいです。

看護学科 平成25年度卒業
岐阜大学医学部附属病院 看護師
皆川 佳那さん
今後も患者さんへの適切なケアを進めていきたい。
祖母が病を患った時、看護師さんがやさしく接してくださり、私も人を助けられる仕事に就きたいと思い、看護師を志しました。岐阜大学で学んで良かったことは、基礎看護学です。しわ一つないシーツ交換から、看護者や介護者の身体的負担を軽減するボディメカニクスまで、看護師として必要なさまざまな知識をしっかりと身につけることができました。また、患者さんの状態を分析・評価してどのようにPDCAサイクルを回していくかを考えた経験が今の仕事にも生きています。卒業後は、教育制度などサポートが手厚いところに魅力を感じ、岐阜大学医学部附属病院に看護師として入職しました。新人担当指導者の制度やメンタルサポート体制があり、とても働きやすい環境だと感じました。心がけていることは、患者さんの日常生活動作能力を低下させないよ うな看護をすることです。患者さんが退院後も自立して生活できるよう、これからも適切なケアを行っていきたいと考えています。

看護学科 令和元年度卒業
岐阜大学医学部附属病院 看護師
伊藤 美彩さん
患者さんや家族の葛藤を支えられる看護師に。
大学の4年間でさまざまな経験を積みたいと考えて岐阜大学へ進学しました。語学の授業では他学科や留学生と交流を深め、多くの友人ができたことも良い思い出です。専門授業で印象的だったのは精神看護学の授業です。患者さんの今の状態だけを見るのではなく、家族歴や生活歴など過去も見るという学びは、もともと人の話を聞くことが好きな自分にとって大変興味深い内容でした。また、救命救急サークルGEMsでは一次救命処置のコンテストで全国2位を受賞し、今の仕事につながる経験ができました。現在は岐阜大学医学部附属病院のICUで意思決定支援係を務め、家族相談士の取得を目指して勉強しています。意思決定支援では、これ以上新たな治療ができない方や、意識のない患者さんに対して本人や家族が納得できるような意思決定を支援しています。大学で学んだ精神学や家族相談士の資格を生かし、ゆくゆくは患者さんと家族の方々が抱える葛藤や悩みを支えられる看護師になりたいと思います。
工学部
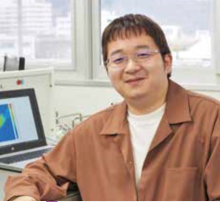
社会基盤工学科
防災コース 4年
後藤 海斗さん
安全になるよう研究成果を応用できる人材になりたい。
自宅から通える国立大学であり、気象学を学ぶことができるため、社会基盤工学科に進学しました。気象学を学べるのは意外だと思うかもしれませんが、この学科は水理学や構造力学といった土木工学を中心に、気象学や衛生工学といった幅広い学問を学べます。通常の講義に加えて、実験やグループワーク、プログラミングといったさまざまな講義が受講できるため、自分自身が高めたいと思っているスキルの向上を図ることができます。研究室は、「自然エネルギー研究室」に所属し、プログラミングによる数値計算を利用して、爆弾低気圧に関係した研究を行っています。研究内容が自身の興味と一致しているため、日々の研究が楽しいです。また、この研究テーマをより深く追求するべく、大学院へ進学したいと考えています。サークル活動では、ジャグリングサークルや工学部自治会に所属し、自分の趣味を増やすきっかけとなり、他学部の人とたくさん交流できたり、大きなイベントの企画や運営を経験できたりしたため、サークルに入って本当に良かったと感じています。

機械工学科
機械コース 4年
梶村 奈々未さん
将来はグローバルに活躍できるエンジニアに。
幼い頃から機械の仕組みを考えるのが好きだったので、工学部に進学しました。印象に残っている授業は CAD 製図の演習です。ソフトウェアを使って3次元モデルを部品ごとに作成し、コンピューター上で合体させるという内容でした。操作が難しく大変でしたが、実際に手を動かしながら設計することができて楽しかったです。勉強する上で心がけていることは、"とりあえずやってみる"こと。向き不向きはやってみないと分かりませんし、必修科目以外の講義も受けることは自分の視野を広げることにつながります。また、2 年生の夏には、大学が提供する「オンライン英語研修プログラム」を活用して、オーストラリアのグリフィス大学に 3 週間留学をしました。海外の学生との交流を通して語学力を向上させ、TOEIC では目標点数を達成。今後は、大学院に進学して専門性と英語力を高めていき、グローバルに活躍できるエンジニアとして社会に貢献したいです。

大学院自然科学技術研究科
物質・ものづくり工学専攻
令和2年度修了
日本ガイシ株式会社
萩原 祥太さん
後押しする制度が充実しています。
岐阜大学工学部の魅力は「多種多様な分析ができる環境があること」と「海外への挑戦を後押しする制度」です。私は大学でセラミック材料の研究をしていました。研究している時は、一つの課題をクリアすると次の課題が出てくるように、分からないことの連続でした。そのたびに大学の機器分析センターで多種多様な分析装置を使い、多角的に分析することで解決の糸口を見つけることができました。
また、海外留学制度も充実しており、私の海外で研究したいという挑戦心を受け止め、韓国への研究留学をサポートしていただきました。私は現在セラミックメーカーで海外向け製品の設計をしています。そこでは大学で培った材料物質の多角的な分析力、海外への挑戦心を生かし、お客様のニーズを満たす最適な性能・特性の製品を提案・提供しています。研究分野に関わらず、自分の興味の対象や視野をいかに広げられるかが大学生活の課題であり、同時に楽しみなことだと思います。皆さんもその大学生活が実りあるものになることを祈っています。

電気電子工学科(現:電気電子・情報工学科)
平成24年度卒業
株式会社ソフィックス
太田 早紀さん
研究室時代の仲間が人生の財産になっています。
工学部でプログラムを学びたいと思い、実家から 1 時間程度で通える岐阜大学に進学しました。工学部は、幅広い分野の基礎を広く学べることが魅力。さまざまな領域に触れる中で学びたいことも変わってくると思いますし、分野の壁に囚われない横断的な考え方が身につくはずです。研究室は、レーザーやエネルギーについて研究を行っている吉田弘樹教授の研究室に所属していました。非常に自由な研究室でしたので、伸び伸びとした雰囲気の中で研究に没頭できたのは非常に楽しかったです。かけがえのない時間を共有した研究室時代の仲間とは今も定期的に連絡をとっており、大げさかもしれませんが人生の財産となっています。就職活動の際は、合同説明会で現在勤めている会社のことを知って入社し、SE として 10 年のキャリアを重ねてきました。世の中には本当にたくさんの会社がありますので、先輩から話を聞くだけでなく、自分でも積極的に探してみると思わぬ出会いがあるかもしれません。
応用生物科学部

生産環境科学課程
環境生態科学コース 4年
水根 一起さん
主体となる研究への理解をより深められる。
小さい頃から生き物が好きで、環境問題にも関心がありました。所属する環境生態科学コースは、生物の多様性を学ぶ「識別実習」など応用生物科学部らしい講義だけでなく、「土壌工学」などの講義を受けることで工学的な領域についても学べることが特徴です。理解を深めたい分野を広い選択肢から選べることは、非常に良いと思います。中でも僕は、「近似」に興味があり、調査方法を工夫して結果を導きだすことに物理の醍醐味を感じています。また、さまざまな領域を横断的に学んできたことで、数式の意味や意図の理解が深まり、さらに面白くなってきました。研究室では、昆虫生態学研究室にて、統計手法やパワーポイントでの発表など先輩のやり方を学んでいるところです。苦手意識のあるコミュニケーション能力を高めるためにアルバイトで接客もしていますが、少しずつ向上してきた感覚もありますので、地道に頑張って大学院でも自分のやりたい研究を実現していきたいと思います。
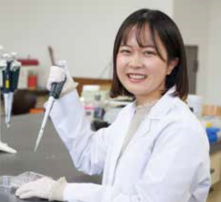
共同獣医学科 5年
中川 慈さん
臨床実習と研究を通して理解を深めていきたい。
物心ついたときから動物が好きで、動物に関わることのできる獣医師を目指しました。岐阜大学の共同獣医学科は少人数なので、先生方からきめ細かく指導を受けられるところが魅力です。学生同士の仲も良く、先輩との距離間も近いので相談がしやすい環境です。思い出深い講義は1年次の「大学教育導入演習」です。鳥取県の畜産試験場と大山放牧場を見学し産業動物の飼養管理に必要な基礎を学ぶとともに、グループワークを通して鳥取大学の学生と交流を深めることができて楽しかったです。現在は、獣医外科学研究室で臨床実習と研究を行い、動物の病気を診察し、治療する際の方法や技術を学んでいます。経験豊富な先生方による診療業務や手術を見学する機会もあり、大いに刺激を受けています。獣医師は、保健所や検疫所など動物病院以外の場所で活躍できるため、進路についてはまだ悩んでいるところですが、研究活動や実習を通して自分に合う道を選択していきたいです。
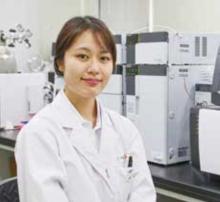
大学院自然科学技術研究科生命科学・化学専攻
令和2年度修了
一丸ファルコス株式会社
藤本 留奈さん
大学院での研究がそのまま仕事に生きています。
高校生の時から理科が好きで、特に生命科学の分野に興味がありました。応用生物科学部を選んだ理由は、生命の仕組みから食品の体への影響まで幅広く学べるところに魅力を感じたからです。所属していた分子生命科学コースの天然物利用化学研究室では、食用の植物や建築用木材など身近な植物の成分を解析する方法や、それらが美容や健康にどのような影響を与えるのかを見る技術を学びました。進路を考えた時、分子科学分野をより深めて大学で得た知識や技術を仕事にしたいと思い、化粧品原料・健康食品原料の研究開発を行う一丸ファルコス株式会社へ就職しました。現在は製品の成分を分析して品質の安定性を見る仕事や、製品開発に向けて天然素材の有用成分を研究する仕事などに携わっています。大学院での研究内容が現在の業務にもつながっており、とてもやりがいを感じています。今後は新しい知識を身につけつつ、健康や美容に役立てるような製品を将来自分で作りたいです。
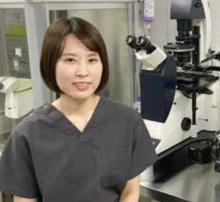
生産環境科学課程 令和元年度卒業
新百合ヶ丘総合病院
土本 和香奈さん
世界"胚培養士"へと導いてくれました。
私は現在、不妊治療を行う産婦人科のある総合病院で胚培養士として勤務しています。生物や動物に関わる職業に就きたいという思いから、応用動物科学コースのある生産環境科学課程を志望しました。講義を通して、生命の始まりである胚発生の分野に出会い、次第に興味を持つようになりました。
研究室では動物発生工学を専攻し、ブタの体外受精に関する研究を行いました。そこで得た学びを生かしたいと考え、ヒトの不妊治療に携わることのできる胚培養士という職業を選択しました。知識や技術だけでなく、とても小さな卵子や精子を大切に、かつ正確に使命感を持って扱うことの重要さは、研究室での経験から学びました。これからもより多くの患者様が子どもを授かれるよう、技術と知識の向上に日々精進していきたいと思います。
社会システム経営学環

社会システム経営学環 3年
菅沼 亜香音さん
卒業後は公認会計士として活躍したいです。
実は高校3年生の段階では、大学に進学するかも含めて進路で悩んでいました。そんな時に高校の先生が教えてくれたのが、社会システム経営学環。ここでなら1年半程度の実習やグループワークなどを通じて社会に出た時に必要なスキルが実践的に身につけられると思い、入学しました。入学後、しばらくは実家のある愛知県豊川市から通学していましたが、より勉学に集中するために下宿をスタート。地元の友達と離れてしまったのは寂しいですが、通学時間が短縮されてかなり楽になりました。講義では、小売業における適切な販売チャネルの選択やプロモーションについて学ぶ「サプライチェーンマネジメント論」が興味深かったです。社会システム経営学環は少人数制で先生との距離も近く、コミュニケーションがとりやすいため、講義においても積極的に議論が交わされて刺激になります。今後は実社会で起きている問題を解決する力を講義と実習で磨きながら、公認会計士の資格取得を目指します。

社会システム経営学環 2年
福井 明生さん
多彩な実習を通じて実践力が身につきます。
私の実家は祖父の代から縫製業を営んでいます。小さい頃から祖父と一緒に働く母の姿を見て育ち、アルバイトで事務作業を手伝うなかで、経営者に憧れを抱くようになりました。そんな中、岐阜大学に社会システム経営学環が新設されたのを知り、専門的に経営を学んでみたいと考えて入学しました。パンフレットを見て一番惹かれたのが、実習の多さ。自分たちで実際の企業が抱える課題を解決する手立てを考え、長期スパンで取り組んでいくことで、社会に出た時に役立つ実践力が身につけられる点に魅力を感じました。投資家向けイベント「IR EXPO」に参加して上場企業の担当者に質問してみたり、川原町の空き家を活用したビジネスを考えてみたり、自分たちで企画した情報誌を発行してみたり。初めての経験ばかりで緊張することも多いですが、その分、貴重な学びがたくさんあるのが楽しいです。今後は「ビジネスデザインプログラム」を選択し、経営についてより深く学んでいきたいです。


